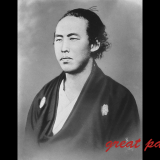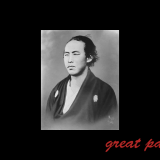偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け
 運営者
運営者
考察
『養子となる者へも伝えてほしいのですが、土佐で流行している長い剣は、すでに伝えているように一対一の喧嘩や、昔話の宮本武蔵の試合などには非常に向いているのですが、現代の戦場では無用です。銃を主要兵器とする場合、刀がなくともよいと考えるべきです。』
帯刀が主流であり、常識。刀が武士の命であり、誇り。時にその誇りでもって、自らの命を終わらせたい。そう考えていた時代に、『銃』の文化がやってきた。その渦中にいる人間は戸惑うだろう。だが、こうして人間は、常に利便性があって高品質な、リーズナブルで合理的な、効率の良い物やサービスに乗り換え、進化を遂げてきた。例えば、
- 『和服⇒洋服』
『人力車⇒車』
『ラジオ⇒テレビ』
『白黒テレビ⇒カラーテレビ』
『ブラウン管テレビ⇒液晶テレビ』
『ベーゴマ⇒テレビゲーム』
『無線⇒スマホ』
『新聞⇒インターネット』
『電球⇒LED照明』
等々、とにかくそれをしていた本来の目的が達成できる、最も利便性があり、リーズナブルで、合理的な物に乗り換え、文化を発展させてきたのだ。もちろんその中には、和服、ラジオ、紙媒体、和食、等といった、ユニークさが卓越していて、価値を失わない物もある。しかし、過去にしがみついて、時代の流れにそぐわない価値やサービスを提供する企業は淘汰されるし、目まぐるしく勢いを寄せる、世の荒波を上手く波乗りすることは出来ない。

アメリカ合衆国元大統領、トマス・ジェファーソンは言った。
『不易流行』とは、変えるべきところは変え、変えないべきところは変えない、という教え、戒め、心構え、教訓である。自分の命と同化するほど身の回りにあった常識。しかし、それに執着して本来の目的を達成できなければ、本末転倒になるのかもしれない。『愛着』だと思っていたものが実は『執着』だった。こういうことがないように、冷静な視野を一つ持ちたい。
※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。
当サイトにある500人の偉人の8000の名言。なぜ『1万』じゃないのか。それは『内省の後半になるにつれ、同じ的を射る言葉が増えた』からです。そしてそれらの真理は、『38の黄金知』としてまとめました。人間が生きる以上未来永劫廃れることのないこの情報を、決してお見逃しなく。
『38の黄金律』へ
中立性と正確性の強化(人工知能)
※ここからは運営者である私の『言葉だけを見て内省した解釈』ではなく、人工知能ChatGPTにおいて『正確性と中立性』を軸に今回の名言を考えて見ましょう。
一般的な解釈
この言葉は、「時代の変化に応じて、従来の価値や道具を見直すべきだ」という趣旨を持っています。坂本龍馬は、幕末の激動期において、武士階級の象徴であった“刀”を手放すことを是とし、より実用的な“銃”の導入を支持しました。この発言は、単なる武器論ではなく、伝統と実利の衝突において“進化”を選ぶ覚悟を表しているとも言えます。社会的・哲学的には、「形式や誇りではなく、目的に適した手段を選ぶ」という合理主義的姿勢として捉えることができます。
思考補助・内省喚起
この言葉は、「自分がいまも“過去の象徴”にとらわれていないか?」という視点を与えてくれます。日々の行動や選択の中で、「かつては正しかった道具・考え方」に固執して、本来の目的を見失ってはいないか――そうした問いかけが、この言葉の本質に触れる道筋になるのかもしれません。
出典・原典情報
※出典未確認
この言葉は複数のメディア・講演・書籍等で紹介されていますが、一次資料(書簡・記録)における明確な出典は確認されていません。伝聞・再構成の可能性があります。
異訳・類似表現
-
「銃で戦うなら、刀はいらない。そこにこだわる必要はない」
-
「新しい時代には、新しい手段を持てばよい」
-
類似:「形式よりも、目的に適した方法を選ぶべきだ」──勝海舟
名言は考えを深めるきっかけになりますが、数が多すぎると、どれを参考にすればいいか迷うこともあります。このサイトには8,000以上の名言がありますが、よく見ると、伝えようとしていることには共通点が多くあります。そこで、似た考えをまとめて、わかりやすく整理した「38の黄金律」という形にしています。必要な言葉をすぐ見つけたい方は、そちらもあわせてご覧ください。
関連する『黄金律』
 『流動変化が避けられないことを知っているかどうかは、人間の運命を大きく変える。』
『流動変化が避けられないことを知っているかどうかは、人間の運命を大きく変える。』