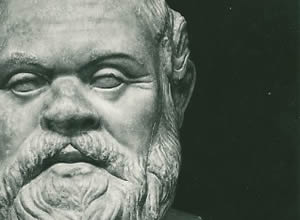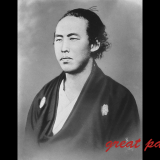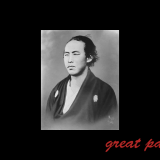偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け
 運営者
運営者
考察
『天下のために働こうとして、土佐藩から一銭一文の資金も援助されることなく、志のある若者たちを50人も養おうとすれば、一人につきどうしても60両は必要となることから、利潤を求めなければなりません。』
『お金』というものは、誰もが必ず一度はぶち当たる、葛藤要因、試練の壁である。金に目が眩んで拝金的になりたくはないし、かといって金がなければ生きていくことが出来ない。金に対し、どう考え、どう対応するかは、その人物が何であるかを、一発で決めることになる。
ソクラテスは言った。
投資家ウォーレン・バフェットの言葉を借りれば、金は人の本性を変えない。金は人の本性を浮きだたせるだけなのだ。しかし、と坂本龍馬は言う。金は絶対に必要なのだと。私も、こと『お金』についてはさんざん悩んだ人間の一人だ。最初は金の存在すら必要性を感じなかったし、途中は拝金的になって、人の道を踏み外した。そんな極端な私に答えを差し出したのは、
孔子の教え、
『義利合一』という概念である。

そう言う坂本龍馬の志は、義の上にあるこそ、成り立つのである。
byインディアンの諺
※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。
当サイトにある500人の偉人の8000の名言。なぜ『1万』じゃないのか。それは『内省の後半になるにつれ、同じ的を射る言葉が増えた』からです。そしてそれらの真理は、『38の黄金知』としてまとめました。人間が生きる以上未来永劫廃れることのないこの情報を、決してお見逃しなく。
『38の黄金律』へ
中立性と正確性の強化(人工知能)
※ここからは運営者である私の『言葉だけを見て内省した解釈』ではなく、人工知能ChatGPTにおいて『正確性と中立性』を軸に今回の名言を考えてみましょう。
一般的な解釈
この言葉は、「理想や志を支えるためには、現実的な経済基盤が不可欠である」という趣旨を持っています。坂本龍馬は、幕末において政治的な理想を掲げながらも、経済活動にも積極的に取り組んでいました。彼が設立した亀山社中や海援隊は、ただの志士集団ではなく、貿易や物資の輸送などを行う実業組織でもありました。この発言は、「志は無償では維持できない」という冷静かつ現実的な視点を示しており、理想と実務を両立させる人物としての哲学を感じさせます。
思考補助・内省喚起
この言葉は、「自分の理想や想いを実現するために、どれだけ現実を直視できているか?」という視点を与えてくれます。日々の行動や選択の中で、「志のためには経済も武器にする」という覚悟を持てているか――理想とお金、思想と数字を切り離さずに両立させるという視点が、この言葉の本質に触れる道筋になるのかもしれません。
出典・原典情報
※出典未確認
この言葉は複数のメディア・講演・書籍等で紹介されていますが、一次資料(書簡・記録)における明確な出典は確認されていません。伝聞・再構成の可能性があります。
異訳・類似表現
-
「理想を掲げるだけでは人は動かせない。金がなければ志も続かない」
-
「維持には金がいる。だからこそ利潤を出す必要があるのだ」
-
類似:「志と経済は両輪である」──渋沢栄一
名言は考えを深めるきっかけになりますが、数が多すぎると、どれを参考にすればいいか迷うこともあります。このサイトには8,000以上の名言がありますが、よく見ると、伝えようとしていることには共通点が多くあります。そこで、似た考えをまとめて、わかりやすく整理した「38の黄金律」という形にしています。必要な言葉をすぐ見つけたい方は、そちらもあわせてご覧ください。