偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け
 運営者
運営者
考察
『力行(りっこう)』とは、力の限り行うことを言う。ソクラテスは言う。
あるいは、ブッダならこうだ。
ここまで考えたら、ショーペン・ハウエルの次の言葉の意味も、簡単に理解できることだろう。

トルストイは、
と言っているが、これはどういう意味だろうか。その答えは、聖書の『伝道者の書 5章』にある。
『見よ。私がよいと見たこと、好ましいことは、神がその人に許されるいのちの日数の間、日の下で骨折るすべての労苦のうちに、しあわせを見つけて、食べたり飲んだりすることだ。これが人の受ける分なのだ。実に神はすべての人間に富と財宝を与え、これを楽しむことを許し、自分の受ける分を受け、自分の労苦を喜ぶようにされた。これこそが神の賜物である。こういう人は、自分の生涯のことをくよくよ思わない。神が彼の心を喜びで満たされるからだ。』
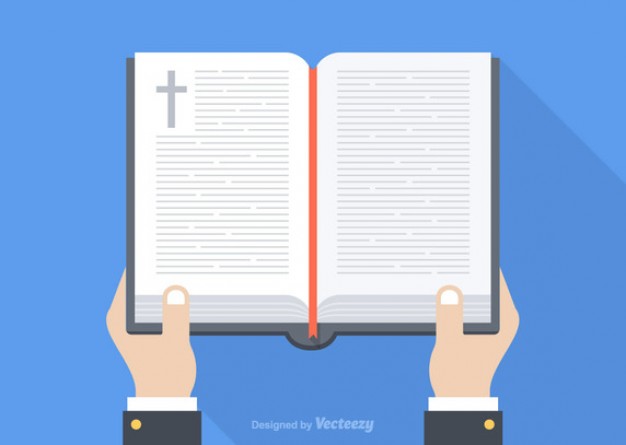
試しに、上に挙げた賢人たちの言う事に逆らってみるといい。それは自由に出来ることだ。
『満足は不満足の中に求むべし、休息は進歩の中に求むべし、安心は力行の中に求むべし。』
つまり、不満足、進歩、力行という『体に負荷がかかっている状態』があってはじめて得られるものがあるのだ。不満足があるから満足が何かがわかる。進歩しているからこそ、途中の休息で英気が養われる。力行して日々に励むからこそ、自分の人生に安心していられる。たとえば、毎日自分の好きな食べ物を食べるとしよう。最初は当然嬉しい。何と言っても大好物を食べているのだ。脳内には報酬系物質のドーパミンが放出され、なんとも言えない多幸感に心が包まれる。つまり、とても満足することができる。

だが、それが毎日続いたらどうだ。本当に初日に味わった満足感と、同じ満足感をその後も毎日得られ続けるだろうか。満足、休息、安心を味わいたい人ならたくさんいる。例えば私の部下がそうだ。そして、私と確執がある、あるいは不和の状態にある人々がそうだ。彼らはいくら表層で『その事実と自分は無関係だ』というシナリオを演じていても、心底でこの事実を忘れることは絶対にできない。では、そのような人が『真の満足、休息、安心』を味わうことはできるだろうか?
自分の命を使い切り、人生で『真の満足、休息、安心』を味わいたいのであれば、それは容易ではないということを覚悟するべきである。見るべきなのは以下の黄金律だ。
本来人は一生、『真の満足、休息、安心』を味わうことはできない。もし味わえると思っているのであれば、それは鈍感である。
※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。
こうして名言と向き合って一つずつ内省したその数『8000』。では、なぜ「1万」ではないのか──それは、内省の後半になるにつれ、『同じ的を射る言葉』が増えてきたからです。そして私はその浮かび上がった真理を、『38の黄金知』としてまとめました。
🧭『38の黄金律』へ
※『38の黄金律』は、有料コンテンツとしてより深い考察をお届けしています。
🔎 名言の背景にある“思想の源流”を探る
※『黄金律』以外の知的コンテンツのほとんどは無料です。








