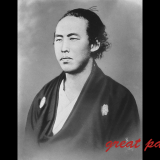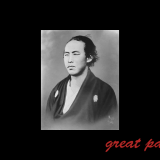偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け
 運営者
運営者
考察
ルネサンス期を代表する作家、フランソワ・ラブレーは言った。
これは、徳川家康も同じことを言っているのだ。
『勝機』とは、『自分が思い立った時』にあるのではないそれであれば、皆が戦いに勝利してしまうのである。私も膿が嫌いで、それが出来た途端に無理に潰すことがあるが、それは往々にして上手くいかない。痛みだけ残るか、あるいは傷痕として遺ってしまうのである。『風林火山』で有名な『孫子の兵法』がある。天の利を活かし、地の利を生かし、人間を過信せず、その枠の外にある力を利用する戦略である。事実、中国の名軍師、李牧は、
と言って、実に『数年』という時間を『山』に徹して勝機を待った。そして敵が油断した一瞬の隙を狙って返り討ちにし、勝利を得たのである。ちなみに、こうした賢人たちの英知を援用し、『まだ時が満ちていない』と言う人間がいるが、彼らは『時間を支配している』のではなく、『人生に支配されている』だけである。
※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。
当サイトにある500人の偉人の8000の名言。なぜ『1万』じゃないのか。それは『内省の後半になるにつれ、同じ的を射る言葉が増えた』からです。そしてそれらの真理は、『38の黄金知』としてまとめました。人間が生きる以上未来永劫廃れることのないこの情報を、決してお見逃しなく。
『38の黄金律』へ
中立性と正確性の強化(人工知能)
※ここからは運営者である私の『言葉だけを見て内省した解釈』ではなく、人工知能ChatGPTにおいて『正確性と中立性』を軸に今回の名言を考えて見ましょう。
一般的な解釈
この言葉は、「物事を成すには、感情や勢いではなく“熟した時機”を見極める必要がある」という趣旨を持っています。坂本龍馬は、幕末の変革期においてただ行動するのではなく、情勢や人心、勢力の動きなどを見極めながら動いていた人物です。時には周囲の焦燥や理想主義を制し、機が熟すのを待つことも重要だと理解していたからこそ、この言葉が生まれたと考えられます。この発言は、「結果を出す者は、ただ闘志を燃やすだけでなく、“引くべきとき”と“動くべきとき”を冷静に見極める戦略眼を持つべきだ」という哲学的な教訓としても捉えることができます。
思考補助・内省喚起
この言葉は、「自分は焦りや感情に流されて早まった判断をしていないか?」という視点を与えてくれます。日々の行動や選択の中で、自らが信じる目的の達成に向けて、今は“動くべき時”なのか“待つべき時”なのかを見極める感覚を持てているか――そうした問いかけが、この言葉の本質に触れる道筋になるのかもしれません。
出典・原典情報
※出典未確認
この言葉は複数のメディア・講演・書籍等で紹介されていますが、一次資料(書簡・記録)における明確な出典は確認されていません。伝聞・再構成の可能性があります。
異訳・類似表現
-
「機が熟さないうちは、手を出すべきではない」
-
「タイミングを誤れば、正しいことでも失敗する」
-
類似:「風が吹くまで、帆は張るな」──孫子
名言は考えを深めるきっかけになりますが、数が多すぎると、どれを参考にすればいいか迷うこともあります。このサイトには8,000以上の名言がありますが、よく見ると、伝えようとしていることには共通点が多くあります。そこで、似た考えをまとめて、わかりやすく整理した「38の黄金律」という形にしています。必要な言葉をすぐ見つけたい方は、そちらもあわせてご覧ください。
関連する『黄金律』
 『耐え忍ぶことができる人間でなければ、大局を見極めることは出来ない。』
『耐え忍ぶことができる人間でなければ、大局を見極めることは出来ない。』