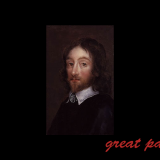偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け
 運営者
運営者
考察
人生が天国や桃源郷、パラダイスの様に楽しいところだったなら、そこでは『より長く生きる』ことに、何の勇気もいらない。快楽に身を任せているだけだ。もっと快楽を味わいたいという欲求に支配されているだけだから勇気などいらない。むしろ、それを断ち切ろうとする気持ちこそ、勇気である。
では、『死より恐ろしいところ』とは一体どういう世界だろうか。この手の話で何度でも引用するのが作家の五木寛之氏は著書『大河の一滴』にある、この一文だ。
あるシベリア帰りの先輩が、私に笑いながらこんなことを話してくれたことがある。
『冬の夜に、さあっと無数のシラミが自分の体に這い寄ってくるのを感じると、思わず心が弾んだものだった。それは隣に寝ている仲間が冷たくなってきた証拠だからね。シラミは人が死にかけると、体温のある方へ一斉に移動するんだ。明日の朝はこの仲間の着ている物をいただけるな、とシラミたちを歓迎する気持ちになったものだった。あいだに寝ている男が死ぬと、両隣の仲間にその死人の持ち物、靴や下着や腹巻や手袋なんかを分け合う権利があったからね。』
これはほんのちょっと前の人間が息をした時代の話だ。もうすぐ、そういう戦争体験者もこの世にはいなくなる。それが何かまた新たな『負の種』を生み出す要因にならなければいいが。
しかしとにかく、地獄のような世界では、命を絶とうとする人間も、大勢いるのが現実。過去の歴史を紐解けば、そういう人の話がわんさか出て来るのだ。例えば仏教の開祖釈迦(ブッダ)が息をした2500年前、あるいはキリスト教の礎イエス・キリストが息をした2000年前はどうだろうか。
当時広がっていた世界は、人間が人間を所有物として扱う時代。身分差別が今よりもうんと根付いていた時代。不治の病の数も、貧困で倒れる人の量も、今とは比べ物にならないくらい多かった。そういう最中、例えばそこが、『地獄のような場所』だったとしたならば、どうしてそこを、『あえて生きよう』と思うことが出来るだろうか。
(死んだ方が楽だよ)
そういう人の声が聞こえてくる。しかし、それでは屈したことにならないだろうか。もっと違う生き方はないのだろうか。立ち上がり、勇気を燃やし、次の時代に出来る限りのバトンを渡す。たとえ自分の人生の間に開かないとわかっている花でも、咲かせようと思う、その人間の気持ちは、尊いのではないだろうか。そして事実、偉大なる先人たちの繋いだバトンは、『平和な国の現在』に、響いているのである。
※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。
こうして名言と向き合って一つずつ内省したその数『8000』。では、なぜ「1万」ではないのか──それは、内省の後半になるにつれ、『同じ的を射る言葉』が増えてきたからです。そして私はその浮かび上がった真理を、『38の黄金知』としてまとめました。
🧭『38の黄金律』へ
※『38の黄金律』は、有料コンテンツとしてより深い考察をお届けしています。
🔎 名言の背景にある“思想の源流”を探る
※『黄金律』以外の知的コンテンツのほとんどは無料です。
関連する『黄金律』
 『この世には、自分にしか歩けない道がある。その道を歩くのが人生だ。』
『この世には、自分にしか歩けない道がある。その道を歩くのが人生だ。』