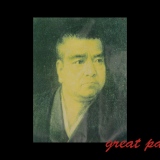偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け
 運営者
運営者
考察
『寧耐(ねいたい)』とは、落ち着いて耐え忍ぶこと。また、『急がば回れ』とは、急ぐときには、危険な近道より、遠くても安全な本道を通るほうが結局早い。という意味。これらの智恵の背景にあるのは、『風林火山』の兵法でもある。『動かざること山の如く』。時にはこういう一手が、道を開拓する。
あるいは中国の名軍師、李牧(りぼく)は、
と言って、実に数年という時間をかけて、敵を欺き、戦いに勝利した。この『数年間山に徹する』ということが、普通の人には本当に出来ない。耐え忍び、機会を待つということはとてつもなく強い意志とエネルギーがいる。例えば、2009年に放送された『記録よりも記憶に残るフジテレビの笑う50年 〜めちゃ2オボえてるッ!〜』で、制作の港浩一バラエティ制作センター局長は、勢いが衰えてきたバラエティ界、日本のテレビ界に対して、こうコメントしていた。
 港浩一
港浩一
だが、あれから8年、2017年現在を迎える今になっても、その『機会』というのは訪れていない。あの言い回しだと、
『いつか昔のように、めちゃくちゃなことをやっていい時代が来る』
というニュアンスが含まれていたが、8年経った今でも彼らの期待通りの結果は訪れていないと言っていい。

つまり、百歩譲って耐え忍ぶことはできても、それで目的を達成できるかどうかは別問題なのだ。李牧の場合、しびれを切らした敵が数年後に攻めてきて、そこを返り討ちにし、勝利を収めることができたが、もしそのまま相手が攻めてこなければその話は武勇伝として語られていない。現在、世界ではイスラム国や北朝鮮等の問題がはびこっているが、この問題は一体いつから続いていて、そしていつまで続くのだろうか。その間、人々はただ耐えて忍んでいけばそれで本当に問題は解決するのだろうか。だが、そこまで考えてももちろん、時代のうねりや、大きな波に逆らうことはできない。見るべきなのは以下の記事だ。
それらの問題は一見すると『流行』と片付けることはできないが、しかし、透明のドラゴンが縦横無尽に暴れまわる様子に瓜二つである。
一つだけ言えることは、このドラゴンに逆らおうとしても無駄だということだ。流行という透明のドラゴンは、黙っていてもいずれあっけなくその場を過ぎ去っていくように、人間が急いで何かしても、何とかならないようなこともある。つまり、その場合は、だとしたら『耐え忍ぶしかない』のだ。そして適応していくしかない。
ちなみに、高速道路には3つ道が並んでいるが、実は、一番早く目的地に到着するのは、一見すると遅い車両ばかりが走る、『左車線』である。追い越し車線である、『右車線』ではないのだ。これもまた、人生という道の開拓の、兵法である。焦っても駄目だ。人間の思い通りにはいかないということを悟るべきである。
※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。
当サイトにある500人の偉人の8000の名言。なぜ「1万」ではないのか──それは、内省が深まるにつれ、「本質を射る言葉」が自然と重なっていったからです。そうして浮かび上がった真理を、私は『38の黄金知』としてまとめました。
🧭『38の黄金律』へ
※『38の黄金律』は、有料コンテンツとしてより深い考察をお届けしています。
🔎 名言の背景にある“思想の源流”を探る
※『黄金律』以外の知的コンテンツのほとんどは無料です。
中立性と正確性の強化(人工知能)
※ここからは運営者である私の『言葉だけを見て内省した解釈』ではなく、人工知能ChatGPTにおいて『正確性と中立性』を軸に今回の名言を考えてみましょう。
名言提示(再掲)
西郷隆盛『急速は事を破り、寧耐は事を成す。』
一般的な解釈
この言葉は、「焦って事を進めれば物事を損ない、じっくりと耐え忍ぶことでこそ成功が得られる」という趣旨を持っています。西郷隆盛は、政治的混乱や軍事的緊張の中で判断を下す場面が多く、経験的に「時を待つ知恵」の重要性を深く理解していました。この言葉は、自己統制・戦略的判断・忍耐の価値を語るものとして、組織運営や人生訓の分野でも評価されています。
思考補助・内省喚起
この言葉は、私たちが「急ぎすぎていないか」「結果を早く求めすぎていないか」という視点を与えてくれます。すぐに答えを出したい、すぐに結果を出したい――そんな衝動をぐっと堪え、熟成の時間を許容する精神がどれだけ備わっているか。耐えてこそ成る、という逆説の真理を心に刻むべきタイミングは、現代においても頻繁に訪れます。
翻訳注意・文化的留意点
この言葉に含まれる表現や語調は、直訳では意味が失われやすい可能性があります。翻訳にあたっては以下のような注意が必要です。
文化的背景:
「寧耐(ねいたい)」という表現には、ただの我慢ではなく、精神的な安定や深い見通しに基づく「静かな忍耐」という含意があります。日本的な慎みと節度の美徳を背景に持つ言葉であり、西洋的な “patience” よりも道徳的重みを伴います。
語彙の多義性:
「急速」は単に “quickness” や “haste” と訳せますが、ここでは「拙速(せっそく)」的な意味合いが強いため、”hasty action” などと補う必要があります。「破る」は物理的破壊だけでなく、計画の失敗や信頼の損壊を含むため “ruin” や “undermine” など文脈に即した訳が求められます。
構文再構築:
漢語調の対句構造を英語では自然に展開する必要があります。
例:
“Haste ruins what patience builds.”
または
“Rushed action often destroys what steady patience would have achieved.”
出典・原典情報
※出典未確認
この言葉は複数の媒体や文献で紹介されていますが、一次資料(書簡・演説録等)における明確な出典は確認されていません。伝聞・再構成された可能性があります。
異訳・類似表現
異訳例:
「焦れば物事を台無しにし、耐えれば成し遂げられる。」
思想的近似例:
「急いては事を仕損じる」──(出典未確認)
「More haste, less speed.」── 英語圏のことわざ
「Patience is bitter, but its fruit is sweet.」── ジャン=ジャック・ルソー
関連する『黄金律』
 『耐え忍ぶことができる人間でなければ、大局を見極めることは出来ない。』
『耐え忍ぶことができる人間でなければ、大局を見極めることは出来ない。』