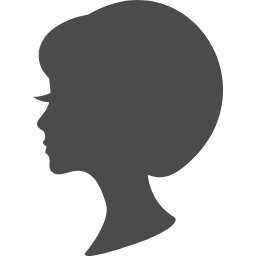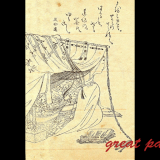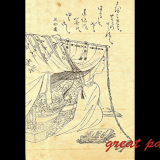偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け
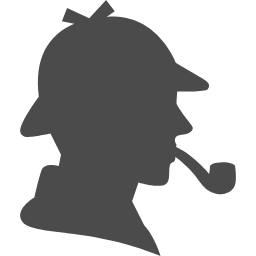 運営者
運営者
考察
この言葉の解説には、『恥ずかしいもの、それは男の心の内。』とだけあったが、忘れてはならないのは『色好む』という部分だ。ここをないがしろにしてはいけない。まるで、全ての男の心の内が、恥ずかしいものであるという風な印象を与える。それは違う。それを言うなら、女に対しても、そっくりそのまま返されてしまうだろう。

そうではなく、『色好む』だ。そして、清少納言が息をした時代背景と照らし合わせて考えるのだ。およそ1000年前、紀元966年頃に誕生したと言われている。『男尊女卑』の考え方が根付いていたのは、つい最近までだ。今でもその名残が残っている。例えば、女が会社で残業などしていたら、白い目で見られた。そんな時代が、すぐ最近まで確かにあったのだ。
そして、この『男尊女卑』という言葉すらなかった時代があった。つまり、『それが当然だ』と考えられていた時代があったのだ。更に遡れば、更に違う概念が浸透していた。日本の女は、今よりも遥かに、奥ゆかしき一生のレールを敷かれていただろう。そこまで考えた時、見えて来るのは『越権的な男』の人間像である。当然、『力』をフル活用してでかい顔をしていた男は、女よりも常に上の立場に立ち、権力を振りかざしていた。
そこで出来るのは、主従関係だ。今で考えてもそうなのだから、その時代であれば、より一層、女は、男に寄り添って生きていく、という考え方が当たり前で、そこに幸せすら覚えていたことだろう。しかし、その中には越権的な男がいたのだ。おそらく、人間の底知れぬ欲望のことだ。数えきれないほどいただろう。女が奥ゆかしいからといって、そこにつけ込んで、私利私欲を暴走させたのだ。不貞を働いた。
そこで、
『ああ、女はこんなにも、美を維持する為に耐え忍んでいるというのに、男はなんて不節操で、だらしがないのだろう。』
と考えたのだ。
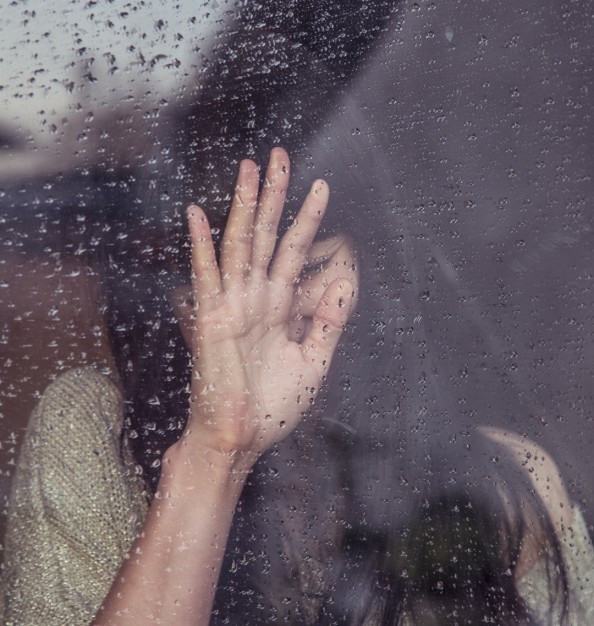
この考え方なら、合点がいく。
※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。
当サイトにある500人の偉人の8000の名言。なぜ『1万』じゃないのか。それは『内省の後半になるにつれ、同じ的を射る言葉が増えた』からです。そしてそれらの真理は、『38の黄金知』としてまとめました。人間が生きる以上未来永劫廃れることのないこの情報を、決してお見逃しなく。
『38の黄金律』へ