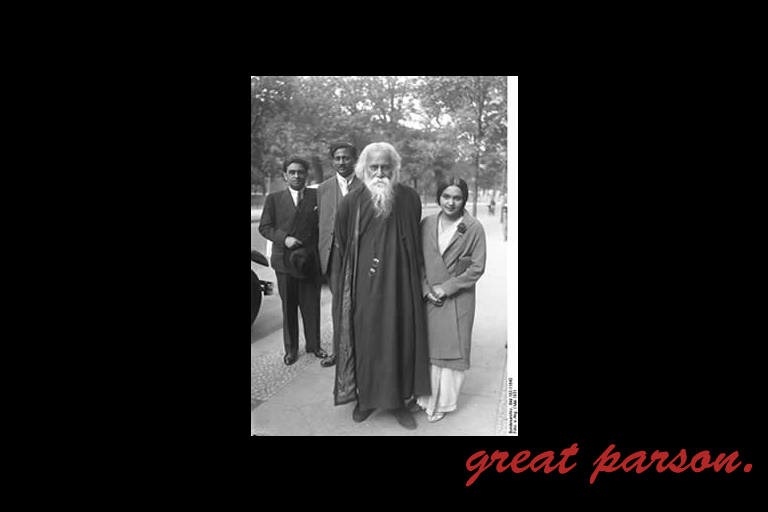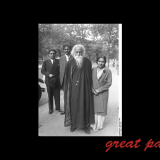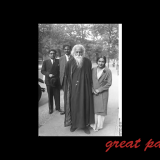偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け
 運営者
運営者
考察
人を理解するときは、その人を愛している。この考え方は、確かに反論の余地はない発想だ。それがすんなり受け止められないのなら、それは『愛』を理解していないのだ。人間は最初、人の気持ちを理解することは出来なかったと言われている。では、初めて理解するようになったのはいつかというと、相手が、『自分と同じように足の小指を角にぶつけた時』とか、そういうのを目の当たりにしたときだというのだ。
(痛そうっ!)
痛みの共感。これが、人間が他人の気持ちを理解した初めてのシーンだったという。
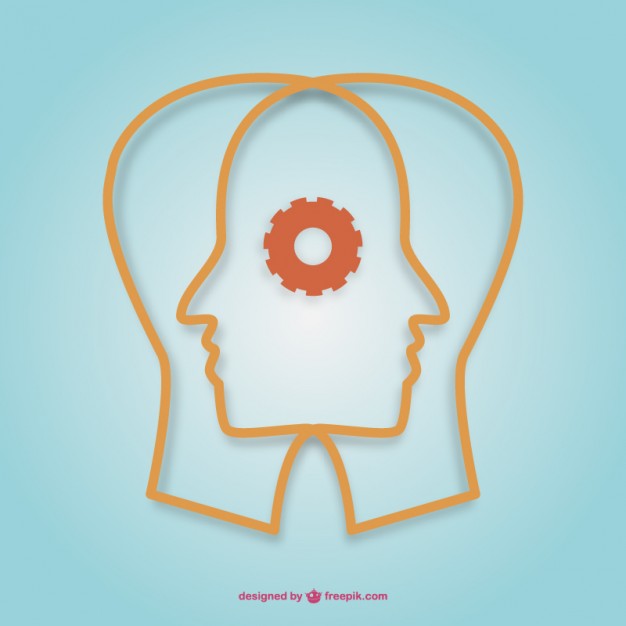
元々は自分の事しか考えることは出来なかった。それが、痛みの共感を皮切りに、徐々に自分以外の存在の気持ちを、理解するようになっていったのだ。そこにあるのは、『愛の移動』である。つまり最初人間は、自分の事しか愛することが出来なかった。タゴールの言うように『愛=理解』ということであれば、尚の事そうだ。自分しか理解できなかった。しかし、それがあるときから『移動』出来ることを知った。
『理解と愛』が、移動できることを知ったのだ。この場合は、他人にである。他人の気持ちを理解したとき、それは自分の中にしか見いだせなかった『自愛』が、相手に移動したときだ。
(痛そう!…身体を大切にして欲しい!)
自分の身体を当たり前のように『ご自愛』するその『愛』が、相手に移動したのだ。つまり、人を理解するときは、その人を愛しているのである。
例えば、殺人事件があって、それを短絡的に見れば、誰しもがその殺人犯を=凶悪という印象付けをするだろう。かし、その事件の背景に、『家族を理不尽に皆殺しにされた。その中の娘の一人には、赤ちゃんがいた。』などという動機があれば、その犯人である父親への印象は、どう変わるだろうか。そこには、多少なりとも『理解』が生まれるはずである。それはつまり、『愛』だ。『共感』したのだ。全ての始まりは、『痛みの共感』だった。
※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。
こうして名言と向き合って一つずつ内省したその数『8000』。では、なぜ「1万」ではないのか──それは、内省の後半になるにつれ、『同じ的を射る言葉』が増えてきたからです。そして私はその浮かび上がった真理を、『38の黄金知』としてまとめました。
🧭『38の黄金律』へ
※『38の黄金律』は、有料コンテンツとしてより深い考察をお届けしています。
🔎 名言の背景にある“思想の源流”を探る
※『黄金律』以外の知的コンテンツのほとんどは無料です。