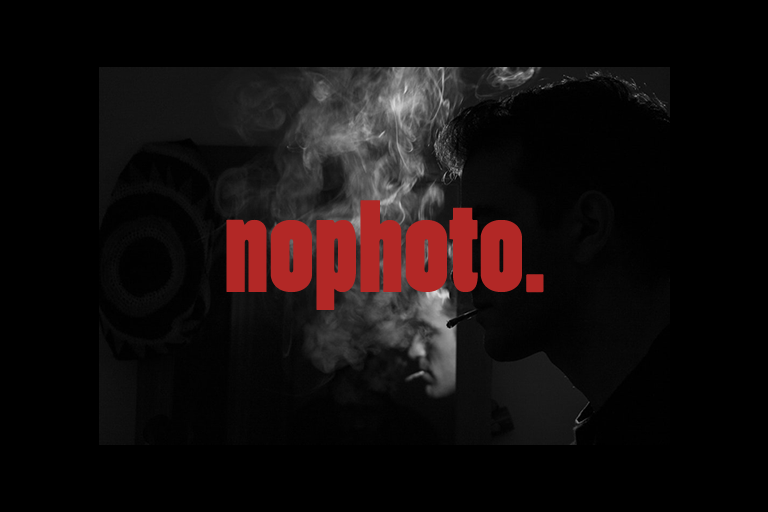偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け
 運営者
運営者
考察
『グローバル化のなかでは、明るい性格のヤツが求められる。明るくアッケラカンとしてる人が、海外で活躍でき、やがてはツキも生む。理屈ばかりで暗い性格はダメ。』
明るい笑顔や笑い声は、まるで『潤滑油』だ。言語や文化、価値観の違いといった壁は思っている以上に大きい。自分の理論に自信を持っている様な人間は、それを淡々と相手に押しつけがちで、それが、それらの壁によって相手に通用しなかった時、人間関係は上手くいかないものである。

私は中国に行って、極めて簡易なものではあるが、仕事をしたことがある。滞在期間は5日間ほどで、その間、現地の人間と、仕事だけではなく、食事をしたり、ビリヤードへ行ったり、酒を飲んだりした。その中で、私が強く感じたのは、『言葉の壁』というよりも、『気持ちは伝わる』という事実についてである。
向こうの社長も、そこで働く若い青年も、皆、私がゲラゲラと笑うのを見て、とても和んでいたようだった。その証拠に、私が帰国した後、私以外のメンバーでもう一度中国へ行ったのだが、私がいないと、どうも静かでつまらない、と向こうの人達が言っていたというのだ。そうして肌で感じたことのある私にはこの言葉の意味がよくわかる。明るい性格は、歯車の形が違うもの同士を円滑にする潤滑油であり、頑なに閉ざされた他人の心の鍵穴に入る、カギである。
※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。
こうして名言と向き合って一つずつ内省したその数『8000』。では、なぜ「1万」ではないのか──それは、内省の後半になるにつれ、『同じ的を射る言葉』が増えてきたからです。そして私はその浮かび上がった真理を、『38の黄金知』としてまとめました。
🧭『38の黄金律』へ
※『38の黄金律』は、有料コンテンツとしてより深い考察をお届けしています。
🔎 名言の背景にある“思想の源流”を探る
※『黄金律』以外の知的コンテンツのほとんどは無料です。
関連する『黄金律』
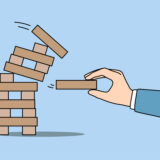 『基礎工事をしない建築物、基礎土台をおろそかにする人間。どちらもその限界は、知れている。』
『基礎工事をしない建築物、基礎土台をおろそかにする人間。どちらもその限界は、知れている。』