・NEXT⇒(各宗教やこの世に存在する教訓の根幹にあるもの)
・⇐BACK(『真理(愛・神)』は、『ある』)
Contents|目次
解釈する人間
『世界がわかる宗教社会学 入門』にはこうある。
契約としての宗教
日本人にとって、ユダヤ教(キリスト教、イスラム教)で理解しにくいのは、神との契約の考え方です。もともと遊牧生活を送る部族社会では、契約が重要です。家畜を預ける、商売する、結婚する、すべてが契約。定住していないので、契約で相手との信頼関係を確実にしておかないと安心できません。
(中略)ユダヤ民族は偶像を拒み、ヤーウェ以外の神を信仰しません。神はその代りに、ユダヤ民族の安全と繁栄を保障します。契約は、ノアの契約、アブラハムの契約、モーセの契約、ダビデの契約…と繰り返し結ばれ、その内容が律法(英語ではlaw、すなわち法律)です。聖書は、この契約をしるす書物なのです。
人間はしばしば神に背きます。そのままだと神の怒りを買い、滅ぼされてしまいます。そこで預言者が現われ、人々に契約を守るよう警告する仕組みになっているのです。

-160x160.jpg) 『世界平和の実現に必要なのは『真理=愛=神』の図式への理解だ。』
『世界平和の実現に必要なのは『真理=愛=神』の図式への理解だ。』
に、ユダヤ教の頑迷な教えを『更新』しようとしたイエスの話については書いた。だが、ユダヤ教もキリスト教もイスラム教も、全てはこの『神(真理・愛)』の絶大な力に気づいているということでは、意見が一致している。違うのは、『それ』に対する解釈であり、『それ』との向き合い方である。
例えばこのユダヤ教の『契約』の考え方。『神に背くと滅ぼされ、神に従えば繁栄する』というもの、あるいは、『契約をしたものだけが救われる』というものは、ユダヤ人がそうやって勝手に解釈しただけで、本当は違うかもしれない。つまり、まずそこに広がっているのが、
『真理(愛・神)から逸れれば逸れるほど虚無に近づく。』
-1-1024x683.jpg)
という事実。これは紛れもないわけだ。暖炉に近づけば温まり、遠ざかると冷えていくように、こうした法則は間違いないこの世に存在している。
そこで、ユダヤ教はこの法則を厳守することに徹底した。従って、
『それ(神・真理・愛)に反するなら、人は人でなくなる。つまり、滅びていくことになる。だが、それ(神・真理・愛)に近づき、その恩恵が得られる範囲内で生きれば、人の心は充足を覚え、豊かに繁栄する。だから契約が必要なのであり、ユダヤ人(このルールを知っている者、厳守する者)だけが救われるのだ』
という発想になった。そしてこうした発想が徐々に様相を変え、『ユダヤ人だけが選ばれし者』という発想を生み出し、それを打破する為にイエス・キリストが生まれた。
信憑性のない人間の解釈
ドイツの哲学者、ニーチェは言った。
『面白いほどよくわかる聖書のすべて』にはこうある。
『旧約聖書』のなかにあるように、人は神との契約で律法を守ることになりました。ところが、その律法さえ守ればあとは何をやってもいいのだ、という考え方にしだいになってきます。ある意味ではマニュアル人間、管理された人間になってしまう。そのような時代のなかで、イエスは自由な生き方を主張しました。これは保守的なユダヤ教徒にいわせると、由々しき問題でした。
その当時は、ただひたすら決まりを守っていれば、あとは何をしてもよかった。金、金、金と追い求めてもよかった。また、律法さえ守っていれば、必ずご褒美を貰えたのです。お金持ちになれたのです。律法に逆らわなければ病気にもおかされない。そのような時代に、そのような考え方をする人々に向かい、自由になりなさいとイエスは言いました。『幸いなるかな貧しいもの』と説いたからです。
それまでは、まず最初に契約に忠実であることが求められていました。これに対し、神のほうから先に愛してくれるーはじめに愛があるのがイエスの出発点です。そういう意味では、あまねく慈悲をかける仏教の出発点もここにあると見られます。
(中略)イエスは、ユダヤ人だけでなく、敵であり、外国人であるサマリア人を含むすべての人々、つまり人種や宗教を超えたすべての人々が隣人であるとしている。イエスの教えが後に全世界に広がるのは、ユダヤ人だけが救われるというユダヤの常識と訣別していた点にある。頑迷に隣人を限定するものではないとイエスは指摘しているのだ。
つまり、わかっているのは、
『真理(愛・神)から逸れれば逸れるほど虚無に近づく。』
-1-1024x683.jpg)
という図式だけで、ユダヤ人だろうがクリスチャンだろうが、ムスリムだろうが仏教徒だろうが、誰だろうがこの図式を重んじれば心を満たされ、一体化すれば威厳を持ち、そこから逸れれば虚無に陥り、そして威厳を失う。
9.11を経て、宗教についての疑問を爆発させた、『利己的な遺伝子』で有名なリチャード・ドーキンスの著書『神は妄想である』にはこうある。
三つのアブラハム宗教のうちでもっとも古く、他の二つの祖先と言って間違いないのがユダヤ教である。
もともとは、猛烈に不愉快な一つの神をもつ一部族のカルトにすぎなかった。この神は、性的規制、焼けこげた肉のにおい、他の神々に対する自らの優越、そして、選ばれた砂漠の民の排他的権利というものに病的にとりつかれていた。ローマ人がパレスティナを占領してた機関に、タルソスのパウロによって、ユダヤ教のそれほど無慈悲ではない一神教的宗派としてキリスト教が興されたが、これは排他性も薄く、ユダヤ人の外の世界に目を向けたものだった。
数世紀後に、ムハンマドとその弟子たちは、もとのユダヤ教の断固とした一神教に回帰したが、その排他性は引き継がず、新しい聖典『コーラン』にもとづくイスラム教を興し、信仰をひろめるために軍事的に征服するという強力なイデオロギーを付け加えた。
キリスト教も同じく、剣の力で広められた。その剣は最初、コンスタンティヌス皇帝がそれを異端のカルトから後任の宗教に昇格させたのちにローマ人の手によって、次に十字軍によって、そしてのちには宣教師を引き連れたスペイン人征服者やその他のヨーロッパ人侵略者や植民地主義者によって振るわれた。
この記事からわかるのは、『最初にユダヤ教があった』ということ。そして、そこから『キリスト教』と『イスラム教』が、『人間の手によって』派生したという決定的な事実だ。ユダヤ人の発想すら間違っていたかもしれないのに、この時、人間が真理(神・愛)から逸れた可能性は十二分にあり得るのである。なぜなら、人間が創り出したものだからだ。
伝統的な教えが『伝言ゲーム』的に人伝いに歪曲していく例として、TBS『クレイジージャーニー』で特集されていた『キルギスの誘拐結婚』の例も挙げられるだろう。キルギスでは昔からの伝統で、男が好きになった女性を誘拐し、家に連れて行き、説得させることができれば、そのまま結婚してもいいことになっている。法律は改正されたのだが、いまだにその慣習は残っていて、現在進行形で行われている。

最初は抵抗するが、多くの女性は『伝統だから』という常識に支配され、それに逆らえずに泣き寝入りし、結婚に至る。女性の一人は言った。
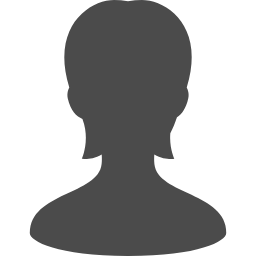 キルギスの女性
キルギスの女性
だが中には、説得に応じず、男側が感情的になり、女性をレイプし、無理矢理結婚式を挙げてしまった例もあった。女はこっそりと両親に電話をし、助けを求め、何とか男側から逃げ出すことに成功した。
だが、その後彼女は首をつって自殺した。彼女には、3か月後に結婚の約束をしていた、婚約相手がいた。
かつて、誘拐結婚で結婚した老夫婦は言った。
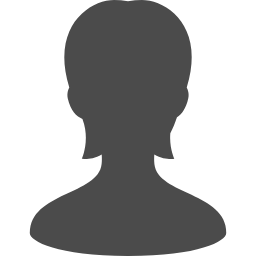 キルギスの老夫婦
キルギスの老夫婦
人から派生していくものに、信憑性はないのだ。
また、『神は妄想である』からは、人間の解釈の信憑性の低さについて、この部分も抜粋できるだろう。
思想の歴史においては、かつては永久に科学の射程外にあると判断されていたことに答が与えられたという実例がある。
1835年に、高名なフランスの哲学者、オーギュスト・コントは星についてこう書いている。
『いかなる方法によっても、われわれはその科学的組成、あるいは鉱物学的な構造について研究することはできないだろう。』
しかし、コントがこうした言葉を書きとどめる以前にすでに、フラウンホーファーは、分光器を用いて太陽の科学的組成を分析していた。いまでは毎日のように、遠い彼方にある星でさえ遠距離から正確な化学組成を分光器で分析することによって、コントの不可知論が誤りであったことが立証されている。

コントのこの不可知論が天文学上、性格にはどう位置づけられるのかはともかく、この教訓的な物語は、少なくとも、不可知論が永遠に真実であると大声で宣言する前に一歩立ち止まるべきだと示唆している。
ものごとの本質は人には認識することが不可能である、とする立場のこと。
不可知論者であることは一見すると賢明に見えるが、しかし、『認識可能な事実』を目の前にして、そこから目をそらして隠蔽し、全てを自然に任せる考え方を貫くつもりなら、この世界に蔓延している一切の『数えきれない失敗の積み重ねでつかみ取った境地(例えば、常識や車や電車や電化製品)』と、無縁でなければならない。
また、目の前で人が死にそうになっているのを見て、『これは神様のご意志だから私が手を出す問題ではない』などと言って、その命を見て見ぬふりをする人間が、あまり『賢明』には見えない。従って、『ものごとの本質は人には認識することが不可能である』という答えを出した人間の解釈は、どこか無責任であり、あまり信憑性が高くない。(追記:ここまで)
-160x160.jpg) 『世界平和の実現に必要なのは『真理=愛=神』の図式への理解だ。』
『世界平和の実現に必要なのは『真理=愛=神』の図式への理解だ。』
にも書いた、『スポットライト 世紀のスクープ』についてをもう一度ここに書こう。この映画は、カトリック神父による少年虐待事件を映画化したものである。実際にあった話だ。
カトリック神父という、極めて大きな影響力を持つ人間が、少年に性的虐待をしていた。ゲーガンという神父が、30年の間に80人もの児童に性的虐待を加えていたというのに、その扱いが極めて小さく、埋もれてしまっていた。つまり、そこには何らかの圧力が働き、真実が隠蔽されかけていたのだ。これは、その真実を、勇気ある新聞記者たちが命懸けで暴こうとし、奮闘する映画だ。
アメリカ等のキリスト教圏内では、カトリックの神父というのはテレビでコメントが放送されるほどの影響力を持つ、極めて重要な立場だ。そうした人物が、その権力の特権を乱用し、不義理を働いていた。
また同じく、『神は妄想である』にはこうある。
アイルランドの場合についていえば、性的虐待がなかったとしてさえ、この国の男性人口のかなりの割合の教育について関与してきた、キリスト教修道士会において児童虐待行為が横行していたのは有名な話である。そして同じことは、アイルランドの女学校の多くを運営していた、しばしばサディストのごとく残忍な修道女についても言えるのだ。ピーター・ミュランの映画『マグダレンの祈り』の舞台である悪名高いマグダレン修道院は、1996年になるまで実在したのである。
それから40年たったいま、折檻に対する賠償を求めるのはわいせつ行為に対する賠償を求めるよりもむずかしいが、そんなことでもなければ遠い過去を思い出すこともなっかったような、はるか昔の犠牲者をそそのかして訴訟を起こさせようとする弁護士は跡を絶たない。
(中略)世界中のカトリック教会は、こうした『犯罪』に関する賠償金を10億ドル以上支払ってきた。そもそもその金がどこからきたかを思い出さないうちは、あなたもほとんど教会に同情するのではなかろうか。
(中略)人を怖がらせる芸術の偉大な達人であるアルフレッド・ヒッチコックは、あるときスイスでドライブをしていて、ふと窓の外を指さしてこう言った。
『あれは私がこれまで見たなかで、もっとも怖ろしい光景だ。』
それは、小さな少年と言葉を交わしている一人の司祭で、彼の手は少年の方におかれていた。ヒッチコックは窓から身を乗り出して、
『おい君、逃げろ!なにがなんでも逃げるんだ!』
と叫んだ。

これでもう十分だろう。『真理=愛=神』だ。つまり、
『キリスト教徒だからといって、神様に仕えている人間だからといって、権威ある人間だからといって、そう広く人々に認知されているからといって、その人物が正しい人間だということにはならない。』
のである。その牧師に『愛』があっただろうか。そんなこと、確認する必要もない。モーセの話で言えば、モーセはその『真理に忠実になった』、つまり、別の言い方で『神に従った』ということになる。そしてそこには『愛』があり、人々の喜びがあった。だが、この神父で言えば、『真理に反することをした』、つまり別の言い方で『神に逆らった』ということになる。そしてそこには『愛』などなく、人々の虚無があった。
前のページにヒトラーやスターリンについて触れたが、ドーキンスはその本で、こうも言っている。
問題は、ヒトラーとスターリンが無神論者であったかということではなく、無神論が一貫して人々を邪悪な行いに『向かわせる』かどうかである。しかし、そうだというどんなわずかな証拠さえ存在しない。
事実として、スターリンが無神論者であったことに疑問の余地はないように思われる。彼はロシア正教の神学校で教育を受け、母親は意向に背いて彼が聖職者にならなかったことへの失望を棄てることができなかったー英国の歴史家、アラン・ブロックによれば、この事実はスターリンを非常に面白がらせたという。ひょっとしたら、聖職者になるための訓練を受けたがゆえに、スターリンは成人してからロシア正教会、キリスト教ならびに宗教一般を激しく批判したのかもしれない。しかし、残虐さを発揮したのはスターリンが無神論者だったがゆえだという証拠はまったく存在しない。
(中略)ヒトラーが無神論者だったという伝説は、きわめて念入りに醸成されてきたものであり、それだけ非常に多くの人が疑問に思うことなく信じており、宗教信奉者たちがいつもきまって、挑戦的にもちだされる。しかしこの問題の真相は、明快というにはほど遠い。ヒトラーはカトリック教徒の家に生まれ、子供のころはカトリックの学校と教会に通っていた。

(中略)キリスト教徒のユダヤ人憎悪は、カトリックだけの伝統だけではない。マルティン・ルターは激烈な半セム族主義者だった。彼はヴォルムス帝国議会において、
『すべてのユダヤ人はドイツから放逐されるべきだ』
と言った。更には、丸々本を一冊費やして、『ユダヤ人と彼らの嘘』という著作を書くことまでしたが、これはおそらくヒトラーに影響を与えただろう。ルターやユダヤ人を『マムシ(毒蛇)の子』と表現しているが、この同じ表現が、ヒトラーの注目すべき演説においても使われている。1922年におこなわれた、ヒトラーが自分がキリスト教徒であると何度も繰り返している演説だ。
『キリスト教徒としての感情が私に、主と戦士たる救い主へと目を向けさせる。かつては孤立し、わずかな数の弟子に囲まれ、これらユダヤ人が何のためにこの世に存在するのかを悟り、彼らと戦うよう人々に命じた、その人へと。そしてその人こそーああ、絶対なる神の真理よ!-受難者としてではなく、戦士としてもっとも偉大なのだ。
一人のキリスト教徒として、一人の人間としての限りない愛を抱きつつ私は、主がついに力強く立ち上がり、手にした鞭でマムシの子を神殿から追放した顛末を述べるくだりを読む。ユダヤ人の毒から世界を守るための神の戦いは、なんと怖ろしいものだったか。2000年の年を経た今日、私は深甚なる感情をもって、神がその血を十字架の上で流さねばならなかったのはこのためであったと、かつてないほど強く確信するのだ。
一人のキリスト教徒として、私は自分が騙かれることなく、真実と正義のために戦う義務を負っている。…われわれが正しい行いをしていると証拠立てるものがあるとすれば、それは日々増えつつある貧窮である。一人のキリスト教徒として、私は自国民に対する義務も負っているのだ。

(中略)ヒトラーがその残虐行為を単独で実行したわけではないことを、ここで私たちは思い出さねばなるまい。恐るべき行為そのものは、兵士やその上官によってなされたが、彼らの大部分はまちがいなくキリスト教徒だった。
(中略)となれば真実は、ヒトラーのキリスト教信仰の告白が誠実なものであったか、それとも、ドイツのキリスト教徒とカトリック教会からの協力をーまんまとーとりつけるためにキリスト教徒だと偽ったかのいずれかである。いずれにせよ、ヒトラー体制が引き起こした邪悪な行いの数々が無神論に源をもつなどとは、これで言えなくなった。
(中略)結局、スターリンは無神論者で、ヒトラーはおそらくそうではなかった。しかし、たとえそうだったとしても、スターリンとヒトラーをめぐるこの議論の、肝心の要点は非常に単純である。すなわち、個々の無神論者は悪事をなすかもしれないが、彼らは無神論の名において悪事をなすわけではない、ということだ。スターリンとヒトラーは極端な悪行をそれぞれ、独善的かつマルクス主義とワーグナー風の狂乱の色合いをもつ、正気の沙汰ではない、非科学的な優生理論の名のもとにおこなったのである。
もう一度言おう。『真理=愛=神』だ。つまり、
『キリスト教徒だからといって、神様に仕えている人間だからといって、権威ある人間だからといって、そう広く人々に認知されているからといって、その人物が正しい人間だということにはならない。』
強要された宗教
ドイツの哲学者、ショーペン・ハウエルは言った。
それなのに私は、両親からクリスチャンになることを強要されて育った。そして彼ら両親は時として信じられない嘘をつき、事実を捏造、隠蔽し、自分たちの思想を正当化するための強硬手段を取った。私が幼かったからといってそれをやったことは、決して許されることではない。私は一生この事実を忘れることはないだろう。
だが、彼らにも良い一面はたくさんあった。だから、殺すほど憎むことはできなかった。
『真理=愛=神』だ。つまり、これらは全て同じものの可能性が高いのだ。何よりこれらは三つとも、『ここから逸れれば虚無に陥り、近づくと心に充足を覚える』という共通点をもっている。特定の人がそこに神様の存在を感じる(神様という支配者に『救われた』と感じる)と思うのは、まるで奇跡を体験した(間違いなく自分たちが考えられるようなものではない、自分たち以外の何かの力が働いた)かのように、心が充足する(温まる)のを覚えるからなのだ。

しかし恐らくそれは『神様の仕業』ではない。なぜなら、特定の人物の利益を満たす為だけに存在する神様など、人間の創り出した虚像だからだ。もし神様という人格神がいると仮定した場合でも、その人は絶対に人間(特にその特定の人物)だけの味方ではない。人が食べるため、着るために殺生され、人のために実験される動物、踏みつぶし、埋め立てて殺す昆虫、伐採する植物、目に見えない小さな生命を含めた、生きとし生けるものすべての味方であることはもちろん、

それ以外の万物すべての味方であり、決して人間だけのために存在しているのではない。この決定的な事実を直視できない視野の狭い人間本位な人間には、どちらにせよ『神(創造者)』の名を語る資格はない。
我々は、この『法則』に触れるか、触れないかということで、心が『充足』したり、あるいは『虚無』に陥るようになっているのだ。『神様』がいるのではない。まるで、暖炉に近づけば暖まり、離れれば冷えていくように、人間がそこに近づけば心は『充足』し、そこから逸れれば心は『虚無』になるのだ。

その法則は目に見えない故、人々はそれを各自で独自解釈し、『真理』と言ったり、『愛』と言ったり、『神』と言ったりしている。しかし実際には、人々はこれらが『何であるか』を正確に言い当てることができないし、未だにその全容も理解できていない。何しろこれらは目に見えないし、形をもっていないからだ。それにこれらは全て、人間が創り出した言葉であり、だとしたらその信憑性は低い。したがって、これら三つの『異なった的を射たはずの言葉』が指し示すものは、もしかしたら『同じもの』の可能性がある、ということは否定できない。

ゴッホは言った。
『真理=愛=神』。この三つの共通点はこうだ。
- 人の目に見えない
- 何ものにも支配されない
- 永久不変である
- 極めて厳かで尊い
- 圧倒的な威厳と力を持つ
- 未だに全容を理解できていない
- 逸れると虚無に近づく
- 近づくと充足を覚える
もちろんこれらが同じものであるという確率は100%ではない。だが、ここまでこれらの共通点が一致するものは他にはなかなかないのだ。この法則に触れ、
- それを『愛』だと認識した人は『愛っていいなあ。』と感じ、
- それを『神』だと認識した人は『神様、ありがとうございます…』と祈り、
- それを『真理』だと認識した人は『ユリイカ!』と叫ぶ。
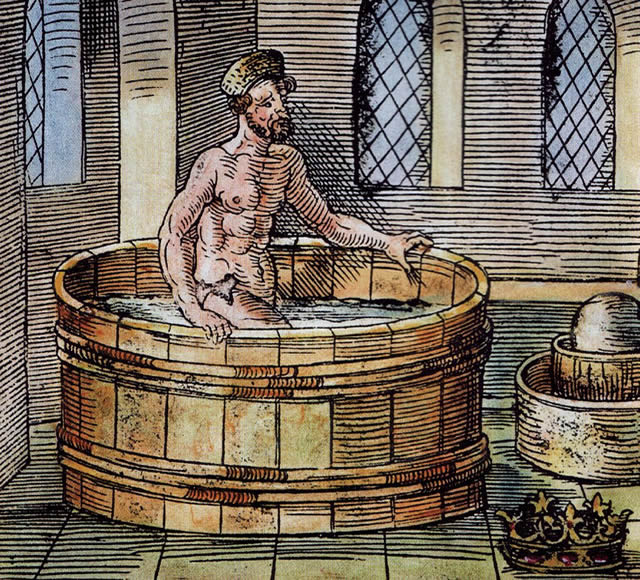
[16世紀に描かれた、風呂に入ったアルキメデスのイラスト]
『神様』と唱える人間が崇高なのではない。『神=真理=愛』の図式を理解し、それらに決して逆らわず、忠実になる人間にだけ、威厳が与えられるのだ。
では、次のページでは各宗教やこの世に存在する教訓の中で、この図式がどれだけ異彩を放っているかを確認していこう。
・NEXT⇒(各宗教やこの世に存在する教訓の根幹にあるもの)
・⇐BACK(『真理(愛・神)』は、『ある』)
-1-940x627.jpg)
-1-160x160.jpg)